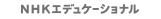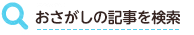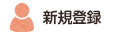赤ちゃん時代からできる ことばを育てる関わり方は?
まだ、お話できないとき、どう関わっていけばよいでしょうか。赤ちゃんのうちからできる「ことばを育てる関わり方」の基本について、田中春野さんに教えてもらいました。
声をかける前によく「見る」

まずは、子どもをよく「見る」ことが大切です。「何が好きか」「何に興味があるのか」をじっくり観察します。何がしたいのかを受け止めて、共感してはたらきかけましょう。
ことばを育てるには、子どもに言わせるのではなく「子どもからの発信」がスタートであることが大事です。
「動き」「変化」をことばにする

子どもと同じものを見ながら、「動き」「変化」をことばにします。「落ちちゃったね」「あいたね」など、動きがあるところにフォーカスして声かけをすると、子どもがそこに着目しやすく興味を持ちやすいです。
子どもの声・動きをまねする・実況中継する

子どもの声や動きをまねするのもいいです。実況中継するのもおすすめです。
オノマトペ(擬音語、擬態語)

オノマトペ(擬音語、擬態語)は子どもの注意をひきます。
子どもの気持ちを代弁する

子どもがたのしんでいるとき、まだことばは出てこないので、「何を考えてるのかな」と、子どもの気持ちをくみとりながら、代弁するように関わってみましょう。その働きかけに声を出したり、手をばたばたしたり、反応するようになります。
赤ちゃんとの関わりで大事なことは?
お子さん10か月のママ 子どもに何かさせようとして、先手を打ってしまうことがあります。ぐっとこらえて、子どもがどんなことに興味を持って、今はどんな遊びが好きなのか見守って、音をことばにしたり、行動をことばにしたりしていけばいいんですね。
丸山桂里奈さん(MC) 私も先手でやっちゃうので、思い出してきました。
赤ちゃんからの発信に応えてあげるのが基本
久保山茂樹さん 赤ちゃんのことばが出はじめるまでは「早くしゃべってくれないかな」「何を話しかけたらいいかな」と焦りがちです。でも、赤ちゃんはもともと発信したい、コミュニケーションしたいのです。その力を持っているのです。 だから、大人が赤ちゃんからの発信に気づくことが大事で、応えてあげるのが基本になります。サインをできるだけ見逃さないようにしましょう。
「心が動く」ときが表現したい、声を出したいとき
久保山茂樹さん 特に赤ちゃんのときは、びっくりして「わっ!」と思わず声が出るなど、「心が動く」ときは、もっと表現したい、声を出したい気持ちになっているので、ことばかけのチャンスです。子どもの横に並んで、「ニャンニャン来たね」「電車来たね」など、ことばにならない気持ちをことばにしてあげましょう。
赤ちゃんは大人のことばをよく聞いているので気をつけて
久保山茂樹さん 赤ちゃんは話せなくても、大人のことばをよく聞いていることを忘れてはいけません。「あ~」とため息をついたり、重い物を運んで「よいしょ」と言ったりするのは、実は大人の心が動いているときです。そういうことばのほうが入りやすいので、気をつけないとあとからまねするんです。
―― ほかにできることはありますか?
よく睡眠をとる。よくかんで食べる。運動する。生活リズムを整える
回答:久保山茂樹さん ことばの育ちには、体や心の発達が関係しています。よく睡眠をとる、よくかんで食べる、運動する、生活リズムを整えるなどが、ことばを育てる土台になります。

PR