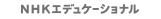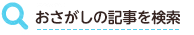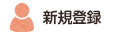番組「すくすく子育て」には、「子育てがしんどい」「自分は親失格」という声が数多く寄せられてきました。なぜ、今の日本では親であることがしんどくなってしまったのでしょうか。2回目は科学の視点から、専門家と一緒に考えます。

専門家: 明和政子(京都大学大学院 教授/脳科学) 鈴木八朗(くらき永田保育園 園長)
今回のテーマについて
「子どもを授かったら、人は自動的に親になる」と思っている人もいるかもしれません。でも最近、そうではないことがわかってきています。
脳科学者の明和(みょうわ)政子さんは、チンパンジーの研究を経て、ヒトの脳と心の発達の原理を明らかにしようとしてきました。今、科学の世界でも注目されている「親性脳(おやせいのう)」について、特に力を入れて研究しています。
「親性脳」は、性差に関わらず、個人が子育てによってゆっくりと発達させる
明和政子さん 「親性脳」とは、子育てを適切に行うために必要となる、ある特定の脳活動のことです。親になった時点でできるのではなく、育児経験を通して次第に発達することがわかりました。生物学的な性差に関わらず、個人が子育てによって、ゆっくりと発達させていくものということが、科学的なエビデンスとしてわかってきました。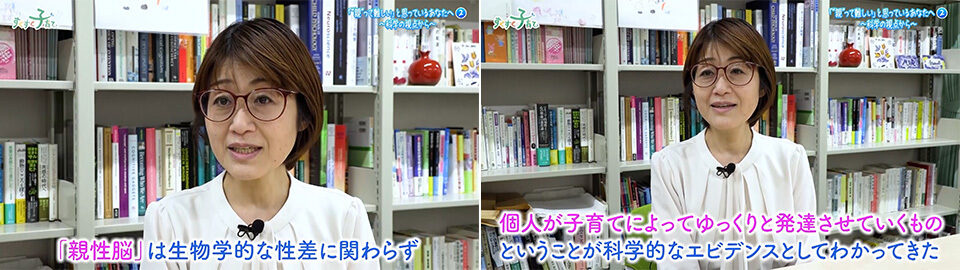
「親性脳」は誰でも発達するもの。それが分かると、「親って難しい」という気持ちが軽くなるかもしれません。
―― 科学の目線からは現在の子育てをどう見ていますか?
現代の環境がヒトの子育てに合っているのかを考える
明和政子さん まずは、人間をヒト(ホモ・サピエンス)と捉えることが大事です。今回は、現代の環境がヒトの子育てに合っているのかどうかを考えてみたいと思います。
卒園するころには「親」として成長している
鈴木八朗さん 子どもが入園したばかりのころの保護者は、体から悩みがわきだしているように感じます。それでも、卒園するころには、新しい悩みもあると思いますが、親としては成長している。このあたりにポイントがあるのではないかと思います。
最後に
PR