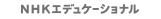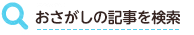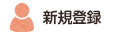人間本来の子育て 令和の「共同養育」とは?
保育園は、現代版「共同養育」の場になるのでしょうか。鈴木さんが園長を務める保育園をたずねました。

こちらの保育園では、子どもを真ん中に、さまざまな人たちがふれ合いながら育つことを大切にしているといいます。

卒園生の女の子が、小さな子どもを抱きしめています。彼女は弟のお迎えのときに、年下の子たちの面倒を見てくれるそうです。ほかにも、多くの卒園生が遊びに来るといいます。

お迎えの時間、パパママでにぎわっています。その中心にいるのは、リクガメの「あーちゃん」。あーちゃんをきっかけに、子どもも大人も会話が生まれます。このような小さな取り組みの積み重ねが、みんなで子育てすることにつながると考えているのです。

園を中心に、子どもも親も、地域の人たちも関わりを深めます。そこに新しい共同養育の可能性があるのかもしれません。
りんたろー。さん(MC) 保育園は子どもを預かってもらうだけの場所ではないのですね。
子どもたちは「群れ」の中で関わり合いながら育つ
鈴木八朗さん 保育園・幼稚園・こども園は、子どもの学びと育ちを支えるのが大事な仕事だと思います。一般的には、先生がいろいろな体験を通して子どもたちを育てているイメージがあると思いますが、実際には子どもたちは「群れ」の中で関わり合いながら育つ部分がとても多いです。
親同士の重なり合いが増えると「子育ての仲間」のコミュニティーが広く強くなる
鈴木八朗さん 親同士の重なり合いを増やすことが、共同養育につながると思っています。いろんな家族がひとつのものに興味を持つと、会話が増えて、重なり合いが増えていきます。例えば、懇談会でひとつのテーマで話し合ったり、保育園で育てた植物を家でも育てたりします。それぞれは小さなことでも、重なり合いがだんだんと増えていくと、「子育ての仲間」のコミュニティーが広く強くなっていくように思います。
りんたろー。さん(MC) 確かに、会話のフックになりますね。
「共通のアンテナ」が立つことが現代の共同養育に重要
鈴木八朗さん そうですね。会話のフックになるのはとても大切です。共通のアンテナが立つことが、現代の共同養育には重要ではないかと思います。
異年齢で遊ぶ環境は自然と「親性脳」が育まれる
明和政子さん 映像にあったように、異年齢の子たちが遊ぶのは大事です。小さいときから多世代の環境だと、自然と「親性脳」が育まれると理解したほうがいいかもしれません。
PR