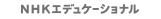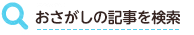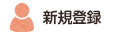子育て中の親1000人を対象に行った番組アンケートでは、子どもの気になる行動について、多くの親が発達の不安を抱えていると回答しました。
かんしゃくがひどい! 突然、泣きわめく…。空想の話ばかりしている…。困った行動をするのは、もともと備わっている「発達特性」によるものかもしれません。子どもそれぞれのよさと違いを認めながら、のびのびと育ち合う環境づくりについて考えます。
専門家: 星山麻木(明星大学 教育学部 教授/特別支援教育)
NHKの番組ホームページでくわしい内容をご覧いただけます。
【ご注意ください】
※放送は、時間の変更や休止になることがあります。
※番組に関する質問には、「すくコム」でお答えすることはできませんのでご了承ください。
ご意見・お問い合わせは、NHKオンライン「ご意見・お問い合わせ」(http://www.nhk.or.jp/css/)までお願いいたします。
PR