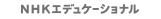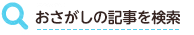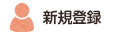シューフィッターに相談したところ、足の小指が当たっているようで、かかとをあわせて履く、正しい履き方を教えてもらいました。履くときに「かかとトントン」をしないと足が前にずれてしまい、サイズが合っていても痛くなることがあるそうです。
ただ、親が一緒のときは履かせてあげられますが、保育園など自分で履くとき、きちんとした履き方をしていないのではないかと気がかりです。
(お子さん3歳・1歳2か月のママ)
―― 靴の履き方は重要ですか?
かかとを踏んで履く・前滑りなどは避けて
回答:落合達宏さん 重要ですね。例えば、靴のかかとをつぶすと、足のかかとを押さえてくれる靴の機能が弱くなります。前滑りすると、お子さんのように小指が当たってしまうこともあります。「つまさきトントン」は、足にも靴にもよくありません。
正しい靴の履き方・履かせ方
解説:吉村眞由美さん

まず、靴をしっかり開いて足を入れ、かかとを合わせます。

「かかとをトントン」して、靴と密着させることが大事です。

靴の「べろ」を内側にしっかりしまって、中心がずれないようしっかり押さえます。
べろがずれないように押さえた状態で、上のテープを「ぎゅー」と引っ張って留めましょう。足と靴が一体化します。
最後に、靴を引っ張るなどして脱げないか確認します。ピッタリと一体化していたらOKです。
―― 「正しい履き方」で履くと、どんな効果がありますか?
正しい履き方はフィットして気持ちがいい。足が自由に動く
回答:吉村眞由美さん 正しい履き方だと、フィットして気持ちいいです。足が痛くなく、自由に動きます。大事なのは、靴のかかとです。かかとをトントンしてフィットさせ固定することで動きやすくなります。歩きはじめも立っているときも、足にピッタリ安定して、いい状態になります。
正しい履き方 ある保育園の「靴教育」
足元から子どもの健康と安全を支える「靴教育」に2年前から取り組んでいる、都内の保育園を訪ねました。

2~3歳クラスの子どもたちが外に出てきました。

先生の「かかとトントン、ぎゅー、ぺったん」という声かけに合わせて、子どもたちは自分で靴を履いて、仕上げは先生が行います。園では、小さいうちから足に合った靴を正しく履いて元気に過ごし、それを「習慣化」することを目標にしています。

園児は全員、足の長さと幅を正確に測っています。3歳以上になると、正しい履き方を身につけやすいつくりの指定の靴を履きます。

また、家でも正しい靴習慣を身につけられるよう、保護者に資料を配付し、定期的に足の大きさを測る方法なども伝えています。保護者から「ちょっと小さそうです」と聞けば、園で正しい計測をして新しいサイズを伝えることもあります。

実は、先生たちも子どもたちと同じ靴を履いています。職員は靴に関する研修を受け、自分の足のサイズを測り、正しい履き方を学びます。
萩原幸さん(園長) まず、子どもたちに接する保育士が、正しいサイズの靴を正しく履くとはどういうことか、そのメリットも理解した上で、子どもたちに伝えることを大事にしています。
4~5歳クラスの担任 目からうろこでしたね。今までと足のフィット感が違いました。「靴を早く履いて、早く遊びに行く」と思っていましたが、「まずは靴を正しく履いて、ケガのないように遊ぶ」という考えに変わりました。

自分で履けない0~1歳のクラスでは、毎回「かかとトントン、ぎゅー、ぺったん」と声かけしながら履かせています。1~2歳クラスになると、自分で履こうとする様子が見られます。
しっかり履いているので、例えば散歩のときも靴が脱げることがないといいます。

ときには靴を脱ぎ、裸足で運動遊びをするなど、さまざまな足の使い方を体験させることも積極的に行っています。裸足でも、靴を履いたときでも、それぞれに適した遊びを思いきり楽しむことで、足の感覚がより育っていきます。

子どもたちは、正しい履き方を覚えると「靴履きマスター」になれます。「靴履きマスター」に、靴履きのポイントを教わりました。

かかとのひも「ループ」を引っ張ると、かかとを入れやすくなります。脱ぐときはテープを「ちょうちょ」の形にしておくと、履きやすくなります。さすがマスターですね。
この取り組みをはじめて2年、どんな成果があったのでしょうか。
萩原幸さん(園長) サイズの合った靴を正しく履くことで、何かあってもふんばれたり、転びにくかったり、運動能力のパフォーマンスが上がっていると感じています。足元が安定するので、姿勢もよくなったと思います。
保護者 子どもが靴のサイズを気にするようになりましたね。靴を買うときには「この靴だときつい」「これだとゆるすぎる」と、はっきり言ってくれるようになりました。
靴が足にぴったり合うのは「気持ちいい」「動きやすい」という感覚を覚え、当たり前と感じること。子どもも大人も身につけたいですね。
正しい「靴感覚」って?
丸山桂里奈さんとりんたろー。さんが、保育園で先生や子どもたちが履いている靴を、正しいサイズ、正しい履き方で履いてみました。

りんたろー。さん(MC) 軽いし、靴底にきちんとクッションがありますね。足の甲がしっかりしまって、足先には遊びがあるから、キュッと力が入ります。
丸山桂里奈さん(MC) 地に足がついている感覚になりますよね。この靴だから正しく履きやすくて、フィットできる気がします。ただ、保育園以外ではこの靴ではないですよね。
吉村眞由美さん はい。この靴はテープを両側から引っ張るので、靴の真ん中のベロがずれず、足全体に包み込むようにフィットします。これが大事です。 市販の靴でも、中心がズレないように押さえながらしっかりテープを留めれば、同じようにフィットした履き方ができます。

りんたろー。さん(MC) ひも靴など、私たちがふだん履いている靴でもできますか?
吉村眞由美さん できますよ。慣れないうちは「今までよりきつい」と感じることが多いのですが、足を「ぎゅっとしめる感覚」が大事です。子どもがきちんと履けたら「履けたね」と言って印象づけてあげましょう。そうすると子どもは「こういうふうにまた履けばいいんだな」と思います。ひも靴でも、かかとをトントンしてくださいね。
―― 靴の履き方で運動能力が上がる、姿勢がよくなることもあるのですか?
よい靴は、たくさん歩かせて・走らせてくれる
回答:落合達宏さん 靴が足にしっかりついて、自由に運動できるので、とてもいいことです。ふだんは雑に履いてしまうことがあっても、正しい感覚が身についている子どもは、走るときや歩くときなど、いざというときに正しく履けるようになると思います。 よい靴は、たくさん歩かせてくれたり、たくさん走らせてくれる。その感覚を覚えるいいチャンスになります。
丸山桂里奈さん(MC) 急いでいるときは立ったまま履ける、楽に履ける靴が履きたくなると思います。
「履きやすい」は「脱げやすい」。災害や事故など本当に急ぐときに脱げてしまう
回答:吉村眞由美さん 立ったまま履けるのはスリッポン(スリップオンシューズ)という、スポッと履く靴ですね。スリッポンの「履きやすい」は「脱げやすい」のです。例えば、災害や事故ですぐ逃げたり走ったりするときにも、脱げにくくフィットした状態で履くことが大事です。スリッポンなどは「おしゃれ、お出かけであまり歩かないとき」、長靴やブーツは「防寒、雨の日に」など目的にあわせて長時間履かせないようにしましょう。
足が力を発揮するようになるまでに足を壊さないようしっかり靴で守りながら正しい靴の感覚を育てていく
落合達宏さん 足が力を発揮するようになるまでには時間がかかります。運動をたくさんさせてあげたいですよね。そのあいだに足を壊さないよう、しっかり靴で足を守って、正しい靴の感覚も育てて、すこやかな足が育っていけばいいですね。
りんたろー。さん(MC) おそろいの靴やかわいい靴を履かせたいと思っていましたが、自分の子どもの足に合った靴を選んであげるのが大事ですね。
PR