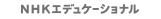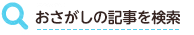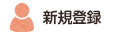ワンオペ育児や小学生きょうだいのいる家庭、どうバランスをとる?
子どもの数が増えたり年齢があがったりすると生活に変化がでてきます。どうやってバランスをとっているのか取材しました。
ワンオペ育児のママ
ママとパパは施設の職員で、長男は4歳、長女は2歳でこども園に通っています。

パパの通勤は片道1時間半かかるので、午前6時50分に出勤です。そのあとはママのワンオペ育児。園に出発するまでの1時間は毎日が綱渡りです。

子どもたちの朝ごはんをみるとチョコがありました。朝の歯磨きをする約束で、朝チョコをOKにしているそうです。いろんなことをやってみて、罪悪感もあるけど余裕がないといいます。

下の子が手を洗っていたら、服がぬれてしまい大号泣。ママは落ち着いてタオルで拭いて、着替えを手伝いました。急いでいるからこそ、冷静に対応します。テレビを見ているお兄ちゃんにも着替えるよう声をかけたり、下の子がお気に入りの靴下が見つからず一緒に探すことになったり、あわただしく時間はすぎます。

8時に子どもたちをこども園に送り、そのまま車で職場に向かいます。車内での30分、自分の時間が癒しのときだといいます。

午後5時15分、こども園にお迎え。7時には、3人で夕食。そのあと、お風呂です。
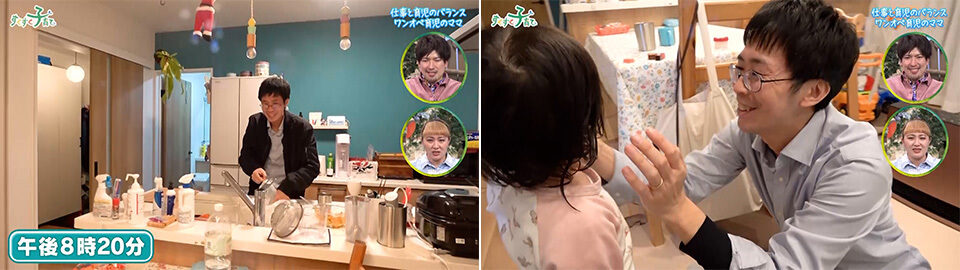
お風呂のときにパパが帰ってきました。子どもたちが寝るまでの1時間が、パパと一緒に過ごせる時間です。パパが子どもたちにクリームを塗ったり歯磨きをしたりします。
子どもたちが寝たあとに、パパは夕食をとって、洗濯をしてから就寝します。
りんたろー。さん(MC) ワンオペでの家事育児は大変です。パパも助けるわけにいかなくて、心苦しいですよね。
ママ 大変ですが、日々のことなので大変と思わずに笑って乗り越えています。
パパ もっと家にいたいけど物理的に無理で。結局ママが頑張ってくれていて、本当に心苦しいですね。
ママ パパは家にいる時間が短い中でも家事をしてくれて、とても感謝しています。ただ、私の職場では子育て中で早く帰りやすい部署にしてもらえたのですが、パパの会社は違うようです。保育園が休みの日曜日に、急に仕事が入ることもあり、きっと「子どもはママがみる」と思っているだろうなと思うと、疲れているときにはイラッとしちゃいます。
丸山桂里奈さん(MC) それはイラっとしてしまいますね。
りんたろー。さん(MC) 本来は、パパもママも同じ前提でないといけませんよね。
パパ 抜けられない仕事もあるし、「帰られたら困る」という空気は感じてしまい、難しいですね。
小学生きょうだいのいる家庭
パパとママは会社員で、小学生(10歳・7歳)と4歳の3人きょうだいです。

午前6時半、朝食づくりはパパの担当。午前7時には、家族5人で朝食です。
小学校1年生の次男は、「ごちそうさま」の後に自分で食器を片づけて歯磨き。だんだん手が離れて、ママ・パパはちょっと楽になったそうです。

家のルールは「どちらかできるほうが、できるときに」。そのとき手があいているほうが家事育児をします。

午後7時、この日はママの帰宅が遅かったので、先にパパと子どもたちで夕食をすませました。
午後7時40分、ママが帰宅。漢字の書き取りがうまくできないと泣く次男を受け止めます。

ママ、パパは、育児の合間に仕事のメールチェックなど細かい仕事をこなします。仕事と育児に、はっきりした区切りはありません。また、お互いの仕事状況をいつも伝え合って共有するようにしています。
ママは「ワンオペだったらいまの仕事はできない、会社の人はパパに感謝してますよ」と話します。
育児休業をとって時短勤務を申請したパパ
子どもと過ごす時間を増やすために、職場にかけあったパパもいます。
(お子さん2歳・5か月のパパ)
番組のアンケートにも、職場や社会に対する声がたくさん寄せられました。
✉ 男性も子どもの体調不良で以前より休みやすくなりましたが、それでもママより休みづらい雰囲気が会社の中にある。制度は権利として使えるという姿勢を上の人たちにも持ってほしい。
✉ 復帰直後はストレスでよく吐いていました。子育てと仕事の両立は親だけの問題ではなく社会の問題だと思います。親はスーパーマンじゃない。
丸山桂里奈さん(MC) そうですよね。両親が離れて住んでいたり、まわりの人に頼れないなど、パパ・ママだけで抱え込んでしまうこともありますよね。
男性もプライベートを重視している。会社の経営戦略に必要な条件に
柴田悠さん 人間はこれまでに夫婦だけで育児してきた時代がなく、夫婦だけでの育児は“無理ゲー“なんです。 ただ、この20年くらいで大きく意識が変わりました。18~25歳の男女へのアンケート調査(※1)があります。この中で「新卒で入社する会社を選ぶ際に将来の仕事とプライベートの両立を意識していますか」という質問に対して、男性の約8割が「意識している」と答えました。男性もプライベートを重視しながら会社を選ぶ意識になっています。若い社員のプライベートを重視するのは、経営戦略上必要な条件になってきていると言えるのです。※1 厚生労働省「令和6年度 若年層における育児休業等取得に対する意識調査」
法定労働時間を減らしていく方向も考えられる
天野妙さん アンケートに「子育てと仕事の両立は親だけの問題ではなく社会の問題だ」という声がありましたね。その通りだと思います。法定労働時間が8時間という設定に無理があるのではないか、例えば7時間に減らすなどの方向も考えられます。子育ての時間を確保していくことを、私たちも働きかけています。
丸山桂里奈さん(MC) 1~2時間でも、全く違いますよね。
りんたろー。さん(MC) 働きたい人は働くけど、ベースを少なくしておくということですね。
天野妙さん そうですね。基準時間を少なくすることにも着眼してほしいと思います。
すくすくファミリー(パパ) 時短勤務ができても業務量が変わらないと負担が大きくなってしまうので、あわせて整理されるといいですね。
りんたろー。さん(MC) 数字では見えない職場のリアルがありますね。
すくすくファミリー(パパ) 育児時短就業給付金なども出てきて、国も時短勤務を推していると思います。職場でも時短勤務しやすい雰囲気づくりをしていってほしいです。
PR