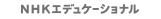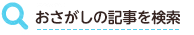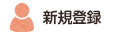子どもの食事を安全に(1)窒息を防ぐ! 食材&調理法
毎日の子どもの食事。窒息事故や食中毒を防いで安全においしく食べる習慣をつけたいですよね。子どもの食事の安全について教えてもらいました。
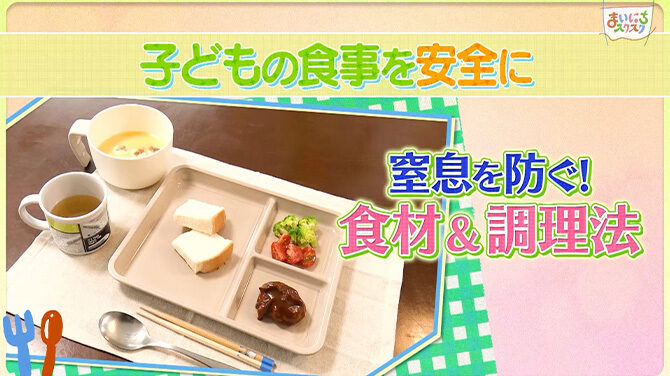
講師: 川口由美子(管理栄養士/母子栄養協会代表理事)
はじめに
川口由美子さん 小さい子どもは、かむ力が弱く、かむ回数が少なく、食事中に注意力が散漫になることから、食品による窒息や誤えんが多いです。過去の事例から、窒息につながりやすい食品がわかっています。特徴をおさえておきましょう。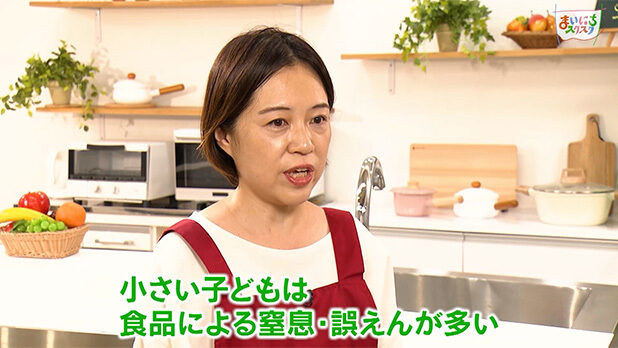
窒息につながりやすい食品
丸くて表面がつるっとしている

白玉だんご、うずらの卵など、丸くて表面がつるっとしているものは、コロコロしていて口の中で滑りやすく、丸飲みして喉に詰まりやすいです。

ミニトマト、ぶどう、さくらんぼなどを子どもにあげるときは、あらかじめ1/4にカットしてあげるようにしましょう。
※必要に応じて皮・種をとりのぞきます

白玉だんご、あめ・ラムネ類など、そのまま与えることが多い食品は、小さいうちは避けましょう。
丸くてかたい

乾いたナッツ、豆類などは、たとえ小さく砕いたとしても、誤って気管に入り炎症を起こすおそれがあります。

6歳未満の子どもには食べさせないようにしましょう。
粘着性が高く飲みこみづらい

パン、ドーナツ、ふかした芋などは、唾液を吸収しやすく、ひと口にたくさんつめこむと飲みこみづらくなります。

食べるときは「水分をとってのどを潤しながら」、小さくちぎって「つめこまない」、そして「よくかむ」ことが大切です。
かたくてかみ切れない・かみちぎりにくい

加熱すると固くなるいかや貝類は、かむ力がつくまで避けましょう。

えびは、薄く切ってから1cm程度に切り分けます。

焼きのりは、2歳ごろまでは細かくするか、刻んだものを使いましょう。
身近な食品で気をつけたいもの

身近な食品にも特に気をつけたいものがあります。例えば、りんご・なしなどです。

1歳半ごろまでは加熱してやわらかくしましょう。
2歳以降でも、生のりんごはかたくて食べにくいこともあります。

例えば、みじん切りにしてしまいフッと吸い込んで肺に入ってしまう、くし切りなど大きく切ってしまいのどにつまってしまうこともあります。

なるべく薄切りにすることでリスクを避けることができます。
心配な場合は、りんごがやわらかくなるまで加熱しましょう。
食材のかたさを調整する

上手に食べているように見えても、大人に近い力でそしゃくしたり飲み込んだりできるのは6歳ごろ。それまでは子どもの様子をみて、子どもの発達に応じて食材のかたさを調整しましょう。
かたさのめやす

食材のかたさが心配になるときには、指を子どもの口に見立てて確認してみましょう。

9か月ころの赤ちゃんは、指の腹でつぶせるかたさ(歯ぐきでつぶせるかたさ)がめやすになります。
※年齢はめやすです。子どもの様子をみて調整してください。
奥歯が生えている場合は、爪をたててつぶせるかたさ(奥歯でつぶせるかたさ)がめやすです。
発達に応じた、食べやすいかたさのめやす

奥歯がはえはじめる1~1歳半は、まだ「かむ力」がついていません。歯ぐきでかめる肉だんごくらいのかたさがいいでしょう。
3~3歳半は乳歯20本がはえそろい、ようやく奥歯でのかみ合わせが安定してきます。この時期まではおとなより少しやわらかめのかたさにしましょう。
食品による窒息を防ぐポイント、参考にしてください。
まいにちスクスク「子どもの食事を安全に」の番組記事
- (1)窒息を防ぐ! 食材&調理法
- (2)窒息を防ぐ! 食べ方&食べさせ方
- (3)子育て家庭の食中毒対策

Eテレの育児情報番組「まいにちスクスク」でこれまでに放送した内容はこちら
PR