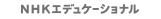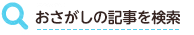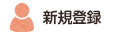長女(1歳4か月)は、生後9か月からトイレに慣れる準備を始めています。例えば、リビングにおまるを置いています。でも、おまるでの排尿はまだ1~2回しか成功していません。誘ってみても、ぬいぐるみを使って「プーさんシーシーしよ。シーシー」と見せてみても、トイレにおまるを置いてみても、あまり効果はありません。
今後、幼稚園に通うようになったら、「他の子と比べて違う」とならないようにしてあげたいと思っています。いろんな情報や周りの声を聞いて、「トイレの準備」を早く始めましたが、そもそも「トイレの準備」はいつから始めるのがいいのでしょうか?
(お子さん1歳4か月のパパ・ママ)
今後、幼稚園に通うようになったら、「他の子と比べて違う」とならないようにしてあげたいと思っています。いろんな情報や周りの声を聞いて、「トイレの準備」を早く始めましたが、そもそも「トイレの準備」はいつから始めるのがいいのでしょうか?
(お子さん1歳4か月のパパ・ママ)
丸山桂里奈さん(MC) 我が家も、子どもが1歳過ぎぐらいにおまるを買ったんです。リビングに置いて座らせていたけど遊んでしまって、そのときはあきらめました。
2~4歳ぐらいで考える
回答:佐藤裕之さん 「1歳半ぐらいから」「2歳ぐらいまでに始めましょう」といったことも言われますが、なかなか難しいですよね。尿意の認識と、ぼうこうの機能の発達が関係するので、実際は2~4歳ぐらいで幅を持って考えたほうがいいと思います。
丸山桂里奈さん(MC) 4歳だと「ちょっと遅いのでは」と思ってしまいます。
佐藤裕之さん 4歳もありうると思いますよ。
―― トイレの準備は、早く始めたほうがいいわけではないのですか?
認識を持たせるのは早くてもいいが、排泄できるようになるかは発達による
回答:佐藤裕之さん 子どもに「トイレで排泄をする」という認識を持たせるのは早くてもいいと思います。一方で、自分で排泄できるかは発達によるのです。
排尿は、ぼうこうに尿がたまってから、自然に括約筋が開いて出されます。この機能は、はじめのうちは反射的で、2~4歳ぐらいになると自分で調節できるようになってきます。4歳以降ぐらいになると、尿意も含めてコントロールできるようになってきます。 ぼうこうの機能は個人差が大きく、1歳過ぎから排尿できる子もいれば、4歳でも未熟でできない子もいます。ぼうこうの機能が発達して、初めて「トイレの準備」ができます。
りんたろー。さん(MC) 子どもが尿意を認識できて、尿意の意思を伝えられるのが適齢期ということですか?
佐藤裕之さん そうですね。その時期に幅があるのがポイントになります。
トイレの準備が早すぎた場合のデメリット
佐藤裕之さん 排尿するとき、本来は括約筋が自然に開いてぼうこうが縮んでいきます。ですが、まだ発達していないのに、例えば「おしっこしなさい」と言われて無理にしようとすると、子どもはおなかに力をいれて、腹圧でおしっこをしようとしてしまう可能性があります。括約筋が開いていないのに腹圧をかけてしまう、ちぐはぐで変な出し方になってしまいます。
また、尿意がまったく育っていない可能性もあり、本来の「尿意を感じて、トイレに行く」練習ではなく、ただトイレに行くことになります。「リラックスして排尿を待つ」と捉えないと、その後のぼうこう機能の安定性や、変な出し方を継続してしまう可能性もあるので、注意が必要です。
排尿を強制するデメリット
本人の尿意を無視して排尿を強制すると、うまく尿意を感じられず、いつトイレに行くべきかわからなくなる可能性があります。また「力を入れて行うもの」という誤った排尿が身についてしまうと尿失禁などの原因になることもあるそうです。

1歳半からのトイレを認識させる方法
丸山桂里奈さん(MC) トイレでおしっこやうんちをすることを子どもにわからせるのに、1歳半ぐらいからできることはありますか?
絵本を活用する。トイレについてきたら教える
回答:佐藤裕之さん トイレが題材になっている絵本などを活用して覚えさせるのはひとつの方法です。 また、子どもが親のトイレについてきて「何をするかな」と興味を持つことがあります。そんなとき、「ここでトイレするんだよ」と教えることもできます。そこで排泄しているところを見せるのがいいわけではありません。子どもによってはびっくりすることもあります。積極的に見せるより、「こういう場所なんだ」と認識を持たせるほうが大事です。
PR